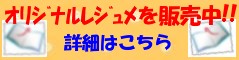審決取消請求事件(平成17(行ヒ)106号)の概説
事件の概要
本事件は、特許無効審決の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について訂正審決が確定した場合は、無効審決が取り消されるとした事件です。
※詳細は判例検索システムで判決文を検索して下さい。
本事件の経緯
①ナイフの加工装置に係る特許権を侵害しているとして、特許権者が損害賠償請求訴訟を提起した。
②被告(侵害者)は、
③明らかな無効理
由があり,本件特許権に基づく差止め及び損害賠償の請求は権利の濫用に当たる旨
主張した。なお,被上告人Y は,平1 成15年7月25日付け審判請求書により,
上記特許について無効審判を請求したところ,審判官は,平成16年1月30日,
第1発明についての特許を無効とする旨の審決をした。
④上告審係属中に、訂正審決が確定した。
[前提] 審決取消訴訟継続中の訂正
最高裁は、大径角形鋼管事件(最判平11年3月9日民集53巻3号303頁)において、審決取消訴訟継続中に特許請求の範囲の減縮訂正が確定したときは、裁判所は無効審決を取り消さなければならないとしました。なお、平成15年改正により、現在では、無効審決を受けた特許権者に訂正の意思があるときは、裁判所が事件を特許庁に差し戻すことができます(特181条)。
本事件の要旨
(3) 第1審における経緯
被上告人らは,同年1
2月7日の第2回口頭弁論期日において,第1発明に係る特許には
上告人は,同年2月6日の第18回口頭弁論期日になって,本件製品は本件明細
書の特許請求の範囲の請求項5(以下「請求項5」という。)のうち請求項1を引
用する部分に係る発明(以下「第5発明」という。)の技術的範囲にも属する旨を
追加的に主張した。被上告人らは,上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却
下されるべきである旨主張するとともに,同年3月15日の第19回口頭弁論期日
において,第5発明に係る特許についても明らかな無効理由がある旨主張した。
第1審は,同年10月21日,本件製品が第1発明及び第5発明の技術的範囲に
属するか否かについて判断することなく,第1発明に係る特許及び第5発明に係る
特許には特許法123条1項1号(ただし,平成5年法律第26号による改正前の
もの。以下同じ。)の無効理由が存在することが明らかであり,本件特許権に基づ
く差止め及び損害賠償の請求は権利の濫用に当たり許されない(最高裁平成10年
(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁
参照)として,上告人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
(4) 原審における経緯
上告人は,平成16年11月2日,第1審判決に対して控訴をした上,平成17
年1月21日付け審判請求書により,請求項5について,特許請求の範囲の減縮を
- 3 -
目的とする訂正審判請求をした(訂正2005-39011号事件)。
被上告人らは,同年2月1日の第1回口頭弁論期日において,第1発明に係る特
許及び第5発明に係る特許には明らかな無効理由が存在する旨主張したが,同年4
月1日に裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)が施行さ
れ,特許法104条の3の規定が本件に適用されるようになったことに伴い,被上
告人らの上記主張は,同日以降,同条1項の規定に基づく主張として取り扱われ
た。
上告人は,平成17年4月11日,上記訂正審判請求を取り下げ,同日付け審判
請求書により,請求項5について,再度,訂正審判請求をした(訂正2005-3
9061号事件)。
上告人は,上記(3)の第1発明についての特許に係る無効審決が確定したことか
ら,同年5月31日の第3回口頭弁論期日において,本件製品が第1発明の技術的
範囲に属する旨の主張を撤回した。これにより,本件訴訟における審理の対象は,
第5発明に係る特許のみということになった。
上記訂正2005-39061号事件について,審判官は,同年11月25日,
訂正審判請求は成り立たない旨の審決をした。上告人は,同年12月22日,同請
求を取り下げた。
原審は,平成18年1月20日に口頭弁論を終結したところ,上告人は,同年4
月18日付け審判請求書により,3度目の訂正審判請求をした(訂正2006-3
9057号事件)。
原審は,同年5月31日に上告人の控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡し
た。原判決は,本件製品が第5発明の技術的範囲に属するか否かについて判断する
- 4 -
ことなく,第5発明に係る特許は,特許法29条2項に違反してされたものであ
り,同法123条1項1号の無効理由が存在することが明らかであって,特許無効
審判により無効にされるべきものと認められるから,上告人は被上告人らに対して
本件特許権を行使できない(特許法104条の3第1項)旨判示したものである。
(5) 原判決言渡し後の経過
上告人は,平成18年6月16日,上告及び上告受理の申立てをした。そして,
同月26日,上記(4)の訂正審判請求(訂正2006-39057号事件)を取り
下げ,同日付け審判請求書により,4度目の訂正審判請求をした(訂正2006-
39109号事件)。
上告人は,同年7月7日,上記訂正審判請求を取り下げ,同日付け審判請求書に
より,請求項5について,特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を
目的として,5度目の訂正審判請求をした(訂正2006-39113号事件。以
下「本件訂正審判請求」という。)。審判官は,審理の結果,同年8月29日,本
件明細書の訂正をすべき旨の審決をし,同審決はそのころ確定した(以下,この審
決を「本件訂正審決」という。)。
本件訂正審決は,別紙1のとおり記載されていた請求項5のうち請求項1を引用
していた部分を,別紙2のとおり訂正するという内容(以下,この訂正を「本件訂
正」という。)を含むものであって,本件訂正に関しては特許請求の範囲の減縮に
当たる。
2 所論は,本件の上告受理申立て理由書の提出期間内に本件訂正審決が確定
し,請求項5に係る特許請求の範囲が減縮されたという本件の事実関係の下では,
原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして,民訴
- 5 -
法338条1項8号に規定する再審事由があるといえるから,原判決には判決に影
響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある(民訴法325条2項)というのであ
る。
3(1) よって検討するに,原審は,本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づ
いて,第5発明に係る特許には特許法29条2項違反の無効理由が存在する旨の判
断をして,被上告人らの同法104条の3第1項の規定に基づく主張を認め,上告
人の請求を棄却したものであり,原判決においては,本件訂正後の特許請求の範囲
を前提とする本件特許に係る無効理由の存否について具体的な検討がされているわ
けではない。そして,本件訂正審決が確定したことにより,本件特許は,当初から
本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされるところ(特
許法128条),前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであ
るから,これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず,上記
無効理由が解消されるとともに,本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製
品がその技術的範囲に属すると認められるときは,上告人の請求を容れることがで
きるものと考えられる。そうすると,本件については,民訴法338条1項8号所
定の再審事由が存するものと解される余地があるというべきである。
(2) しかしながら,仮に再審事由が存するとしても,以下に述べるとおり,本
件において上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うこと
は,上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延
させるものであり,特許法104条の3の規定の趣旨に照らして許されないものと
いうべきである。
ア特許法104条の3第1項の規定が,特許権の侵害に係る訴訟(以下「特許
- 6 -
権侵害訴訟」という。)において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべ
きものと認められることを特許権の行使を妨げる事由と定め,当該特許の無効をい
う主張(以下「無効主張」という。)をするのに特許無効審判手続による無効審決
の確定を待つことを要しないものとしているのは,特許権の侵害に係る紛争をでき
る限り特許権侵害訴訟の手続内で解決すること,しかも迅速に解決することを図っ
たものと解される。そして,同条2項の規定が,同条1項の規定による攻撃防御方
法が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるとき
は,裁判所はこれを却下することができるとしているのは,無効主張について審
理,判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。こ
のような同条2項の規定の趣旨に照らすと,無効主張のみならず,無効主張を否定
し,又は覆す主張(以下「対抗主張」という。)も却下の対象となり,特許請求の
範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も,審理を不
当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば,却下されること
になるというべきである。
イそして,前記1の事実関係の概要等によると,①被上告人らは,既に第1審
において,第5発明に係る特許について無効主張をしており,平成16年10月2
1日に言い渡された第1審判決は,特許法に同法104条の3の規定を新設した平
成16年法律第120号の施行前であったが,前掲最高裁平成12年4月11日第
三小法廷判決に従い,上記無効主張を採用して上告人の請求をいずれも棄却したこ
と,②上告人は,平成16年11月2日に上記第1審判決に対して控訴を提起し,
平成17年1月21日に請求項5について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正
審判請求をしたが,同年4月11日にこれを取り下げ,同日再度請求項5について
- 7 -
訂正審判請求をしたこと,③上記再度の訂正審判請求については,同年11月25
日に同請求は成り立たない旨の審決がされ,上告人は同年12月22日に同請求を
取り下げたこと,④そこで,原審は平成18年1月20日に口頭弁論を終結した
が,上告人は同年4月18日に3度目の訂正審判請求をしたこと,⑤原審は同年5
月31日に上告人の控訴をいずれも棄却したが,その理由は,第1審判決と同じく
被上告人らの上記無効主張を採用するものであったこと,⑥上告人は,同年6月1
6日に上告及び上告受理の申立てをしたが,その後3度目の訂正審判請求を取り下
げて4度目の訂正審判請求をし,さらに4度目の訂正審判請求を取り下げて5度目
の訂正審判請求をしたのが本件訂正審判請求であること,以上の事実が明らかであ
る。
ウそうすると,上告人は,第1審においても,被上告人らの無効主張に対して
対抗主張を提出することができたのであり,上記特許法104条の3の規定の趣旨
に照らすと,少なくとも第1審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の
審理においては,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含め
て早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして,本件訂正審決の内容
や上告人が1年以上に及ぶ原審の審理期間中に2度にわたって訂正審判請求とその
取下げを繰り返したことにかんがみると,上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主
張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだす
ことができない。したがって,上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審
の判断を争うことは,原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を
原判決言渡し後に提出するに等しく,上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵
害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず,上記特許法104
- 8 -
条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。
4 以上によれば,原判決には所論の違法はなく,論旨は採用することができな
い。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官泉徳
治の意見がある。
裁判官泉徳治の意見は,次のとおりである。
私は,本件上告を棄却するとの多数意見の結論には同調するが,その理由を異に
する。本件訂正審決が確定し,特許請求の範囲が減縮されたことにより,特許査定
が当初から減縮後の特許請求の範囲によりされたものとみなされるに至ったとして
も,民訴法338条1項8号所定の再審事由には該当しないから,原判決につき判
決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとすることはできないと考え
る。
1 一般に,特許権侵害訴訟において,原告の特許権を侵害したと訴えられた被
告が,特許法104条の3第1項の規定に基づき,当該特許は特許無効審判により
無効にされるべきものと認められるから,原告においてその権利を行使することが
できないという権利行使制限の抗弁を主張した場合には,原告は,当該特許に係る
特許請求の範囲のうち被告主張の無効理由が存在する部分(以下「無効部分」とい
う。)が,訂正審判を請求して特許請求の範囲を減縮することにより排除すること
ができるものであること,及び,被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の
技術的範囲に属することを主張立証して,権利行使制限の抗弁の成立を妨げること
ができる。訂正審判の請求により無効部分を排除することができる場合には,特許
法104条の3第1項にいう「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきも
のと認められる」ことにはならないのである(ちなみに,最高裁平成10年(オ)
- 9 -
第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁も,
「訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから」特許権に
基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されない旨判示している。)。そし
て,被告において,権利行使制限の抗弁を成立させるためには,既に特許無効審判
が請求されているまでの必要はなく,特許無効審判の請求がされた場合には当該特
許が無効にされるべきものと認められることを主張立証すれば足りるのと同様に,
原告において,同抗弁の成立を妨げるためには,既に訂正審判を請求しているまで
の必要はなく,まして訂正審決が確定しているまでの必要はないのであり,訂正審
判の請求をした場合には無効部分を排除することができ,かつ,被告製品が減縮後
の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証すれば足りる。
すなわち,原告は,訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができ
ることを主張立証することにより,訂正審決が現実に確定した場合と同様の法律効
果を防御方法として主張することができるのである。原告は,現実にも,事実審口
頭弁論終結時までに,訂正審判の請求を行うことが可能であり,請求が理由のある
ものである限り,通常,訂正審決の確定を得ることも可能であるが,被告の権利行
使制限の抗弁の成立を妨げるためには,現実に訂正審判を請求し,訂正審決を確定
させておくまでの必要はないのである。
以上のように,訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができる
こと,及び,被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属する
ことは,被告の権利行使制限の抗弁が成立するか否かを判断するための要素であっ
て,その基礎事実が事実審口頭弁論終結時までに既に存在し,原告においてその時
までにいつでも主張立証することができたものである。原告としては,事実審口頭
- 10 -
弁論終結時までに,上記の主張立証を尽くして権利行使制限の抗弁を排斥すべきで
あり,事実審が,当事者双方の主張立証の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証
の結果として,権利行使制限の抗弁の成立を認めた以上,事実審口頭弁論終結後に
なって,原告が訂正審判を請求し訂正審決が確定したとしても,訂正審決によって
もたらされる法律効果は事実審口頭弁論終結時までに主張することができたもので
あるから,訂正審決が確定したことをもって事実審の上記判断を違法とすることは
できないのである(なお,最高裁昭和55年(オ)第589号同年10月23日第
一小法廷判決・民集34巻5号747頁,最高裁昭和54年(オ)第110号同5
7年3月30日第三小法廷判決・民集36巻3号501頁参照)。
民訴法338条1項8号は,再審事由の一つとして,「判決の基礎となった行政
処分が後の行政処分により変更されたこと」を掲げている。事実審が特許法104
条の3第1項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は,当初
の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく,上記のとおり,訂正審判の
請求がされた場合にはそれが認められるべきものであるか否かも考慮の上,換言す
ると,訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから,
その後に訂正審決が確定したからといって,上記判断の基礎となった行政処分が変
更されたということはできない。仮に,原告が,事実審口頭弁論終結時までに,訂
正審判の請求をした場合にはそれが認められるべきものであることを主張しなかっ
たため,事実審がその点の判断をしなかったとしても,その後に原告が上記主張を
行うことは許されないから,訂正審決が確定したから上記の再審事由が存するとい
うことはできないのである。
更に付言すると,事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定したから再審事由が存
- 11 -
し,原判決を破棄すべきであるというためには,訂正審決が確定したことにより,
原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるということがいえ
なければならない。しかし,訂正審決が確定しても,原告において,被告製品が減
縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証しない限
り,権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならな
い。また,被告においても,減縮後の特許請求の範囲による特許がなおも特許無効
審判により無効とされるべきものであることを主張立証することができ,この主張
立証に成功したときは,権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあると
いうことにはならない。すなわち,これらの原被告の主張立証を待たなければ,原
判決に法令違反があるということができないところ,法律審である上告審ではこの
ような原被告の主張立証を審理することができない。そうすると,訂正審決の確定
により特許請求の範囲が減縮されたとしても,原判決につき判決に影響を及ぼすこ
とが明らかな法令の違反があるとすることはできないのであるから,この点からし
ても,訂正審決が確定したから再審事由が存するということはできないのである。
2 したがって,本件においても,原審口頭弁論終結後に本件訂正審決が確定し
たからといって,民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するということはで
きず,原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとするこ
とはできない。
3 ちなみに,特許権侵害訴訟においても,事実審が特許権者の請求を認容した
場合は,当該特許権の成立,効力を前提として,その侵害行為があったことを認定
するものであるから,事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり,当該特許権に係る
特許査定処分が変更されたときは,民訴法338条1項8号にいう「判決の基礎と
- 12 -
なった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」に該当する。しかし,本件
は,特許権侵害訴訟ではあるものの,原審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者
の請求を棄却した事案であるから,特許権者の請求を認容した事案とは区別する必
要がある。
4 なお,最高裁平成14年(行ヒ)第200号同15年10月31日第二小法
廷判決・裁判集民事211号325頁は,特許権者が,特許取消決定の取消しを求
めて訴えを提起し,事実審で請求を棄却する旨の判決を受け,事実審口頭弁論終結
後に訂正審判を請求し,上記訴訟事件が上告審に係属中に訂正審決が確定したとい
う事案に係るものである。特許取消決定は,対世的に特許権がはじめから存在しな
かったものとする決定である。上記第二小法廷判決は,上告審係属中に当該特許に
ついて特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には,原判決の基礎
となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして,原判決には民訴法
338条1項8号所定の再審事由がある旨判示した。上記第二小法廷判決は,特許
取消決定により取り消された特許査定処分を審理の対象としているのであるから,
審理の対象である特許査定処分が訂正審決により変更されたことは民訴法338条
1項8号所定の再審事由に該当すると判断したものである。しかし,特許権侵害訴
訟は,特許権そのものを審理の対象として特許権の効力を対世的に確定したり消滅
させたりするものではないのであって,特許取消決定の取消しを求める訴訟とは異
質のものである。したがって,上記第二小法廷判決の判示を,特許権侵害訴訟にお
いて事実審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案に適用す
ることはできない。
私見
従来の判例を踏襲していますし、法改正によって今後はこのような事例がなくなると思われますので、これが論文試験で直接問われる可能性は低いと思います。但し、短答試験で問われる可能性はありますので、「特許無効審決取消訴訟の上告審係属中に、特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合、無効審決が取り消される」という結論だけは覚えておきましょう。
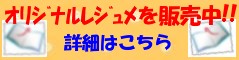
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る