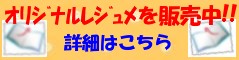特許権侵害差止請求事件(平成16(受)997号)の概説
事件の概要
本事件は、特許権のすべての範囲について専用実施権者に専用実施権を設定している特許権者が、その特許権の侵害者に対して専用実施権の侵害を理由として、侵害製品の販売差止を求めた事例です。※詳細は判例検索システムで判決文を検索して下さい。
また、地裁では、特許法68条及び77条2項を根拠に、「特許権に専用実施権が設定されている場合には、設定行為により専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、差止請求権を行使することができるのは専用実施権者に限られ、特許権者は差止請求権を行使することができない」と判断された点について、最高裁の判断が注目された事件です。
[前提] 専用実施権を設定により制限される特許権
特許法100条1項では、「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定され、特許権者は特許権の侵害者に対して差止請求権(特許法100条1項)を有します。
一方、特許法68条では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」と規定され、専用実施権が設定された範囲については、特許権者による権利行使が制限されています。
そのため、専用実施権が設定された範囲について、特許権者による差止請求権の行使が制限されるか否かについて、学説・判例の対立がありました。
本事件の要点
最高裁の判断によれば、特許権について専用実施権を設定したときであっても、特許権者にも差止請求権の行使を認める必
要があるので、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するということです。その理由は、次の3つです。
①特許法100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠がない。
②専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益がある。
③特許権の侵害を放置していると、専用実施権が消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性がある。
つまりどういうこと?
つまり、専用実施権を設定した特許権者にも、差止請求権の行使を認める必要がある。よって、特許権について専用実施権を設定したときであっても、特許権者は自己の特許権に基づいて差止請求権を行使できるということです。
本件は、専用実施権が設定されている場合の、特許権者の特許権者の取り得る措置として重要な事例ですので、その理由と共に、結論をしっかり覚えて下さい。
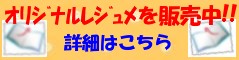
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る