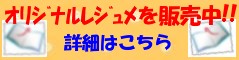商標法6条-7条の2
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
商標法6条(一商標一出願)
第一項
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
・商6条1項,2項違反は、拒絶理由にはなるが、異議申立理由及び無効理由にはならない。特、実、意と同様である。
・「商品(役務)を指定して」の「商品(役務)」の解釈について、指定商標の単位は、指定方法にかかわらず施行規則による細分類の商品を一単位として数える。但し、包括表示による指定も認められる(第25類履物など)(網野)。なお、包括表示の場合は、その包括表示に含まれる個々の指定商品(役務)ごとに出願を分割できる。
・審査基準には、指定商品(役務)について、商6条1項は、指定商品等の表示の明確性を要求しており、商6条2項は、区分に従っていることを要求している旨が規定されている。
①指定商標等の表示が不明確で、商品等の区分に従っていない場合、例えば、第7類機械器具とすると、商6条1項,2項違反として拒絶される。
②指定商品等の表示が不明確で、商品等の区分に従っている場合、例えば、第2類全ての商品とすると、商6条1項違反として拒絶される。
③指定商品等の表示が明確で、商品等の区分に従っていない場合、例えば、第9類時計とすると、商6条2項違反として拒絶される。
・商標等の区分のみが記載されているときは、補完命令が出される。
・商品等のみが記載されているときは、補正命令が出される。
・「商標」が二以上の場合は、6条違反として拒絶される、また、分割もできない。
・他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商標と同一の類に分類する。
・商品は、その主たる原材料に従って分類する。
・容器は、その収容する商標と同一の類に分類する。
・複数の区分の商品等を指定することができるのは、出願手続を簡素化するためである。
・指定商品又は指定役務の表示中に、特定の商品又は役務を表すものとして登録商標が用いられている場合は、原則として、商6条1項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由が通知される。
・指定商品又は指定役務の表示は不明確であるが、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと判断できるときは、商6条1項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由が通知される。例えば、第2類全ての商品、第29類食肉,その他本類に属する商品等である。
第二項
前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
・審査対象を明確にするためである。
・指定商品の欄に商品と役務とが記載されている場合は、商品及び役務の区分に従っていないので、商6条2項に反する。例えば、16類「雑誌、雑誌による広告の代理」とある場合は、16類「雑誌」35類「雑誌による広告の代理」と補正する必要がある。なお、区分が増加するので手数料の支払いが必要となり、不納の場合は補正命令がなされる。
・区分に関して、意匠では、「経済産業省令」で定め、商標法では、「政令」で定めている。
・「ニューヨークでデザインされたメガネ」は指定商品にできる。
・指定商品又は指定役務の表示は明確であるが、政令で定める商品及び役務の区分に従っていないときは、拒絶の理由を通知する。(例) 「第36類雑誌による広告の代理」(「第35類雑誌による広告の代理」と補正することができる。)、「第16類雑誌, 雑誌による広告の代理」(「第16類雑誌、第35類雑誌による広告の代理」と補正することができる。)。
第三項
前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
・異なる区分の商品又は役務同士であっても、類似となる場合がある。
商標法7条(団体商標)
第一項
一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
・諸外国との国際的調和を進める必要があるため、団体商標と通常の商標とは異なる性質を有する(団体自身が使用する必要はなく、出願当初から商標権者とは異なる構成員による使用が予定されており、構成員は構成員たる地位を有する限り商標の使用をする権利が認められる)ため、及び地域おこしや特定業界の活性化のために独自ブランドによる特産品作りが求められている時代の要請があるため、本規定が設けられた。
・事業協同組合とは、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合を指す。その他特別の法律により設立された組合とは、農業協同組合法により設立された農業協同組合等をいう。
・これらに相当する外国の法人とは、業として商品の生産や役務の提供をする事業者を構成員に有し、且つ法人格有する外国の団体、例えば、欧州諸国のぶどう酒組合等をいう。
・財団法人は財産の集合であり事業者を構成員として有していない為、株式会社、持ち株会社、日本たばこ産業株式会社等はその構成員にあたる株主が事業者であってしかも会社がその事業について自己の商標を使用させるとは考え難い為、フランチャイズチェーンはフランチャイザーとフランチャイジーの間の事業契約によって成立するものであり団体とその構成員の関係にはない為、それぞれ団体商標の登録を受けることができない。
・団体商標の主体として、商法により設立された会社を除く法人格を有するその他の社団が追加された。その他の社団には、商工会議所法に基づく商工会議所、商工会法に基づく商工会、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)等の特別の法律により法人として設立された社団が含まれる。
・本項違反は、拒絶、異議、無効理由となる。
・一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいう。
第二項
前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
・構成員のみ又は構成員及び団体が使用するものには適用できるが、団体のみが使用するものには適用できず、拒絶・異議・無効理由となる。
・団体商標であっても単なる産地表示の商標登録は認められない。単なる産地表示は自他商品識別力を有さず、産地表示を特定の団体に独占させるのはその団体に属さない生産業者や販売業者が使用できなくなりかえって地域おこし等に支障を生じるおそれがある(当該産地における全同業者が一つの団体の構成員であったとしても将来に渡ってアウトサイダーがでない保証はない。)からである。また、団体商標であっても使用により自他商品識別力を備えた場合、登録が認められるからである。
・通常の一般的登録要件を具備する必要がある。
第三項
第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
・証明書面が提出されない場合は、補正命令が出される。
・必ずしも出願と同時に提出する必要はない。
商標法7条の2(地域団体商標)
第一項
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
・地域団体商標の登録要件は、①出願人が法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合等であり、設立根拠法において構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨が規定されていること(主体要件)、②構成員に使用をさせる商標であること、③地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる文字商標であること(対象とする商標の要件)、④地域の名称が出願前から使用している商品又は役務と密接な関連性を有していること(地域の名称と商品又は役務の密接関連性の要件)、⑤周知となっていること(周知性の要件)である。
・商3条2項は全国的に需要者に高い浸透度をもって認識されていることを要するが、本条では全国的な周知性は要求されず、近隣都道府県で周知であれば良い。但し、日本国内で周知であることを要する。
・団体商標の主体要件との違いは、組合の設立根拠法において不当に構成員たる資格を有する者の加入を制限してはならない旨の規定が定められていることを要する点にある。地域における生産者や役務提供者等が広く使用を欲する商標であり、一事業者による独占に適さないため、使用を欲する事業者等が当該商標を使用する途が可能な限り妨げられないようにしたものである。
・構成員に加えて団体自身が使用する商標であっても良い。
・商3条1項1号及び商3条1項2号に該当する場合は、地域団体商標としても登録を受けることはできない。何人も使用できるようにしておく必要性が特に高いためである。
・これに相当する外国の法人とは、業として商品の生産や役務の提供をする事業者を構成員に有し、法人格を有する外国の団体であって、構成員資格を有する事業者の加入が不当に制限されないことが担保されている団体をいう。
・事業協同組合とは中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合をいい、その他の特別の法律により設立された組合とは、農業協同組合法により設立された農業協同組合、水産業協同組合法により設立された漁業協同組合等をいう。
・商3条1項6号を除く、商3条1項3号、4号、5号については商3条2項によっても登録を受け得る。
・地域の名称+商品又は役務の①普通名称、②慣用商標、又は、③普通名称又は慣用商標と産地若しくは提供地に付される慣用文字の組み合わせ、を合わせたものが客体となる。
・商標中の商品(役務)の名称はその指定商品(指定役務)と一致していることが必要である。例えば、「〇〇りんご」との商標について、「りんごジュース」や「りんごケーキ」を指定商品とすることはできない。
・地域団体商標に認められない例:①地域の名称のみからなるもの又は地域の名称が含まれないもの、② 普通名称のみからなるもの又は慣用名称のみからなるもの、③ 普通名称又は慣用名称のいずれも含まないもの、④商7条の2第1号から3号に規定された文字以外の文字や、記号又は図形を含むもの、⑤識別力が認められる程度に図案化された文字からなるもの(図形等との組み合わせ商標や特殊文字の商標等の識別力を有する商標は、改正前でも登録を受けられたので、地域団体商標制度で登録を認める必要性がないからである)
・地域団体商標と同一又は類似の商標の使用に関する商26条1項2号又は3号の適用については、自他商品(役務)識別機能を発揮するような態様で商標が使用されていれば、商26条1項2号又は3号の規定の適用はなく、地域団体商標に係る商標権の効力が及ぶものと考えられる。
・一般社団法人は含まれていない。
・商標権者である団体は、構成員による商標の使用の条件を定めることができ、構成員は当該条件に従って、指定商品等について、登録商標の使用をする権利を有することとなる。
・密接な関連性を有すると認められる地域とは、例えば、主要な原材料の産地、商品の製法が由来する地などである。
・同一地域において、複数の団体が同一の商標を使用しており、その商標が特定の一つの団体又はその構成員の業務に係る商品(役務)を表示するものとして周知となっていると認められない場合には、いずれの団体も独自に登録を受けることはできない。また、複数の団体がいずれも周知となっている場合には、需要者に混同をもたらすおそれがあるため、商4条1項10号により、登録を受けることはできない。
・複数団体がまとまって共同出願をした場合(又は、出願の後には共同出願に名義変更をした場合)であっても、全体として登録要件を満たすと判断されれば登録が認められる場合もある。
・地域団体商標と文字部分が同一又は類似の図形入りの先願登録商標が存在する場合であっても、かかる先願登録商標は図形部分が商標の要部となるため、地域団体商標と類似せず、後願の地域団体商標の商標登録出願は拒絶されないと考えられる。一方、地域団体商標の後願で文字部分が同一又は類似の商標については、地域団体商標と類似し、商4条1項11号に該当するものとして登録が認められないこととなると考えられる。
第一号
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
・普通に用いられる方法で表示する文字とは、普通の態様で表示する文字商標、例えば、標準文字をいう。
・地域の名称のみの商標を対象としなかったのは、一般に、地域ブランドについては地域の名称のみの商標が用いられることが少ないためである。また、地域の名称のみの商標についても登録を認めると、類似商品(役務)に地域の名称のみの商標を使用したときには権利侵害となり、同一又は同名の地域において他の商品(役務)を生産・販売、提供等する者による地域の名称の正当な使用を過度に制約し、その事業活動を萎縮させるおそれがあるためである。
第二号
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
・慣用名称とは、例えば、「織」「紬」、「焼」、「塗」、「彫」、「細工」、「豚」、「温泉」、「梨狩り」、「牛」、「漬」の名称等である。
・商品又は役務の特質を表示する文字と普通名称からなるものであっても、需要者に全体として特定の商品又は役務を表示するものとして使用され、認識されている名称は慣用名称に含まれる。例えば、「天然あゆ」「完熟トマト」等である。
第三号
地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
・産地等に付される文字として慣用されている文字とは、例えば、「本場」「特産」「名産」等である。
・産地等に付されるものとは認められないものとは、例えば、「特選」「元祖」「本家」「特級」「高級」等である。これらの文字が加わった商標は、地域団体商標として登録を受けることができない。
第二項
前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
・「地域の名称」には、旧地名、旧国名、河川名、山岳・湖沼・海域名等も含まれる。また、略称でも良い。
・本項に反する場合、本条1項に反するとして拒絶、異議、無効理由となる。
・地域の名称とは、①その商品の産地、②その役務の提供場所、又は、③これらに準じる程度にその商標若しくはその役務と密接な関連性(商品の製法が地域に由来している場合、地域において生産された原材料を用いて商品が生産されている場合等)を有する地域(地域の略称も可)、の名称である。
・商品の産地とは、例えば、①農産物について、商品が生産された地域、②海産物について水揚げ又は漁獲された地域、③工芸品について、主要な生産工程が行われた地域等である。
・役務の提供の場所とは、例えば、①温泉について、温泉が存在する地域等である。
・役務と密接な関連性を有すると認められる地域とは、例えば、①加工品の主要原材料が生産等された地域(例、そばの実の産地・硯の石の産地)、②重要な製法が発祥し由来することとなった地域(伝統的製法の由来地)等である。
・地域の名称として取り扱われる場合とは、例えば、①その地域において生産している場合、②役務をその地域において提供している場合、③不可欠な原材料や主要な原材料の産地が着目され取引されている商品であり、その地域において生産されたその主要な原材料を用いた当該商品を生産している場合、④その地域に由来する製法で生産している場合等がある。
・地域団体商標の「地域」には外国の地域をも含む。内国民待遇の原則によるものである。
第三項
第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
第四項
第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
・証拠方法とは、例えば、①新聞、雑誌、書籍等の記事、②公的機関等の証明書、③パンフレット、カタログ、内部規則、④納入伝票、注文伝票等の各種伝票類等である。
・主体要件を満たさないことが明らかな会社や個人等による出願の場合には、実体審査を行うまでもなく方式審査の段階で出願を却下することが適当である。このため、出願人に対して主体要件を満たすことの証明書の提出義務を課し、提出がない場合には出願を却下している。
・地域団体商標が、商標中の地域の名称と密接な関連性を有する商品又は役務以外の商品又は役務について使用されるときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると考えられる。従って、地域団体商標の指定商品(指定役務)については、例えば、「〇〇産の△△」、「〇〇における△△の提供」のように地域的な限定を付す必要がある。
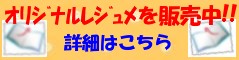 参考書・基本書について
試験対策・勉強法について
改正・判例解説
短答試験の無料講座
過去問の解説
論文試験の無料講座
選択科目について
免除制度の説明
口述試験について
転職について
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る
参考書・基本書について
試験対策・勉強法について
改正・判例解説
短答試験の無料講座
過去問の解説
論文試験の無料講座
選択科目について
免除制度の説明
口述試験について
転職について
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る