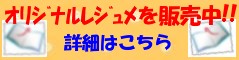意匠法46条-50条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
意匠法46条(拒絶査定不服審判)
第一項
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
・拒絶査定不服審判においては、補正却下に対して不服を申立てられない。
・従来の短い審判請求期間では、審判請求の当否を十分に検討できないという問題があった。そこで、H20年改正により審判請求期間を拡大した。
第二項
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
意匠法47条(補正却下決定不服審判)
第一項
第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
・意匠法では広範な補正が認められていないので、補正による権利付与の遅延等の障害がない。また、願書の記載及び図面などに本質的な変更を加える補正は、要旨変更に該当する場合がほとんどであるため、補正がなされた場合であっても要旨変更か否かの判断に解釈が入り込む余地が少なく、客観的な判断が可能である。そのため、補正却下処分に争いがある場合もその審理に時間を要しないので、迅速な権利付与の障害とはならない。よって、補正却下決定不服審判が存続している。
・補正却下決定不服審判において、登録すべき旨の審決はできない。補正却下の当否が争われるだけである。
・補正却下決定不服審判を請求した場合であっても、補正却下後の新出願はできる。
・拒絶査定不服審判にて補正却下決定に対する不服を申し立てることはできない。
・従来の短い審判請求期間では、審判請求の当否を十分に検討できないという問題があった。そこで、H20年改正により審判請求期間を拡大した。
第二項
前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
・不責事由による延長が可能である。
意匠法48条(意匠登録無効審判)
第一項
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
第一号
その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第二項若しくは第三項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項 において準用する同法第二十五条 の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
・願書に添付した図面が相互に一致せず意匠の特定性を欠くものであるときは意3条1項柱書き違反として無効理由に該当する。但し、図面の不一致等でも軽微な瑕疵の場合は、意匠が特定できる限り無効理由にならない。訂正審判もなく、無効理由とすると意匠権者に酷だからである。
・意7条、意8条、意10条1項は拒絶理由ではあるが、無効理由ではない。なお、意10条1項が無効理由に挙がっていないのは、意匠登録後に本意匠と関連意匠が類似していないという理由で無効とするのは意匠権者にとって酷だからである。対して、意10条3項は本意匠の表示の欄を削除しても登録されない。類似の無限連鎖を防止するためである。
・補正の要件違反、新規事項追加、訂正の要件違反は無効理由にない。
・組物が全体として統一がない場合であっても無効理由とはならない。形式的瑕疵だからである。
・拒絶査定となった先願に係る意匠に類似している場合であっても、拒絶査定出願は先願の地位を失うため、無効理由とはならない。
・重複出願が看過されて一方が登録となり、協議することができないことにより他方の出願が拒絶された場合、拒絶された出願の存在を理由に無効審判を請求できる。
第二号
その意匠登録が条約に違反してされたとき。
第三号
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
第四号
意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
第二項
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
・意匠法においても、無効審判は何人も請求できる。
第三項
意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
第四項
審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
意匠法49条(意匠登録の無効の審判)
意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
意匠法50条(審査に関する規定の準用)
第一項
第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
・拒絶査定不服審判において補正却下された場合、それを理由として東京高等裁判所に訴えを提起する以外に不服を申し立てる方法はない。
第二項
第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
第三項
特許法第五十条 (拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
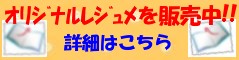 参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る