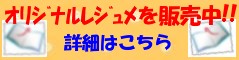インク・カートリッジ事件(平成18(受)826号)の概説
事件の概要
本事件は、インクタンクに関する特許の特許権者が我が国及び国外で譲渡した特許製品の使用済みインクタンク本体を利用し、これに加工するなどして製品化されたインクタンクについて、特許権者による権利行使が認められた事例です。※詳細は判例検索システムで判決文を検索して下さい。
また、知財高裁において、①当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)、②当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)には、特許権は消尽しないと認定された点の判断が注目された事件です。
[前提] 特許権の消尽とは?(BBS事件)
特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(特許権者等)が我が国において特許製品を譲渡した場合、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されません(最高裁平成7年(オ)1988号)。
インク・カートリッジ事件の要点
最高裁の判断によれば、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、あくまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されると解されます。
そして、特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断されます。さらに、特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が考慮の対象となります。また、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となります。
国際消尽について
最高裁は国際消尽についても触れており、我が国の特許権者等が国外において特許製品を譲渡した場合に特許権の行使が制限される対象となるのは、あくまで我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品そのものに限られると認定しました。そのため、我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、我が国において特許権を行使することが許されると解されます。ここで、特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合と同一の基準に従って判断されます。
つまり、国際消尽の場合についても国内消尽の場合と同様に、加工前の特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権の行使が認められます。
インク・カートリッジ事件における新たな製造についての判断
最高裁は、被上告人製品(純正品)にはインク補充のための開口部が設けられておらず、上告人製品(リサイクル品)においては、純正品のインクタンク本体の液体収納室の上面に穴を開け、そこからインクを注入した後にこれをふさいでいるとし、このような加工等の態様は、純正品のインクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものであると認定しました。
また、リサイクル品は、使用済み純正品を再使用して、発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであると認め、発明の実質的な価値を再び実現し、発明の作用効果を新たに発揮させるものであると認定しました。
その上で最高裁は、インクタンクの取引の実情などの事情を総合的に考慮して、リサイクル品は、加工前の純正品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものであると認めました。その結果、使用済み純正品を利用して製品化されたリサイクル品について、特許権の行使が制限される対象となるものではないとし、被上告人の特許権の行使を認めています。
つまりどういうこと?
つまり、①特許権者等が国内又は国外において譲渡した(特許権が消尽した)特許製品の加工品であっても、発明の本質的部分に係る構成を欠くに至っている加工前の特許製品(使用済み製品)に対して、加工や部材の交換等を行い、
②加工前の特許製品と同一性を欠く新たな製品を製造した場合であって、
③上記加工や部材の交換等の結果、発明の本質的部分に係る構成を再び充足させ、発明の実質的な価値を再び実現し、発明の作用効果を発揮させている場合は、新たな特許製品の製造にあたる、ということです。
④但し、新たな特許製品の製造にあたるか否かの判断に際しては、取引の実情等の事情も総合的に考慮されます。
私的解説
特許権者が特許製品を販売した場合、その特許製品の転得者(例えば、購入者が転売した場合の第三購入者)に対して、特許権の侵害を主張することは、特許製品の円滑な流通を妨げる等の理由から(又は、二重に利益を得ることになるため)許されません。つまり、特許権が消尽します。
ここで、特許製品が消耗品であった場合に、その使用済み特許製品を回収し、加工(例えば、インクカートリッジへのインク補充や、使い捨てカメラへのフィルム充填等)を加え、その加工済み製品を販売等する行為に対して、特許権者が特許権の侵害を主張できるかどうかというのが本事件の問題です。
結論を簡単にいうならば、特許権が消尽するのは譲渡された製品そのもの(同一物)であり、処分品(使用済み製品)の使える部品を使って新しい製品を製造し、それが新たな特許製品の生産と判断できるならば、特許権の侵害を主張できる、ということです。そして、新たな特許製品の生産か否かを判断する際には、様々な事情を考慮される、という判断基準が示された点で重要な判決であると思います。
本判決の、もう1つのポイントは、新しい製品が特許製品と同一ではないことが必要であるということです。つまり、加工後の製品が特許製品と同一であった場合は、新たな特許製品の生産にはあたらないということです。具体的にどの程度を同一とするのかは、判例の蓄積を待たれるところですが、個人的には、インクカートリッジの取り外し可能な部品を外して(穴を開けずに)インクを充填し、再度部品をはめて販売する場合は、インクカートリッジ自体が完全に同一であり、新たなインクカートリッジの生産に当たらないと思います。一方、取り外し不可能な部品を取り外してインクを充填し、異なる代替部品をはめて販売す場合は、インクカートリッジ自体が異なるので、新たなインクカートリッジの生産に当たると思います。
いずれにしても、弁理士試験、特に論文試験では聞きやすい(事例が作りやすい)テーマになります。事例を考えるならば、「使用済みインクカートリッジにインクを充填して販売している甲に対して、インクカートリッジについての特許権者乙が特許権の侵害を主張できるか?」、「甲の販売するインクカートリッジが、特許製品に加工を加えない同一製品である場合はどうか?」等でしょうか。ですので、BBS事件も含めて判決の要点をしっかり覚えて下さい。
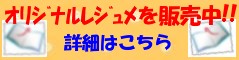
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る