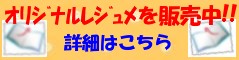秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(平成20(許)36号)の概説
事件の概要
本事件は、特許権の侵害差止め等を求める仮処分命令申立事件において、特105条の4第1項に基づく秘密保持命令の申立てが許されるか否か、すなわち、同項の「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」が仮処分命令申立事件が含まれるのかが争われた事件です。
※詳細は判例検索システムで判決文を検索して下さい。
本事件の経緯(概要)
①特許権者は、自己が保有する特許権の侵害行為の差止め等を求める仮処分命令の申立てをした。
②債務者(差し止めを求められた者)は、仮処分事件に提出を予定している準備書面等に営業秘密が記載されているとして、特105条の4第1項に基づき、特許権者の代理人又は補佐人である相手方らに対する秘密保持命令の申立てをした。
③原審は、特105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」には、特許権の侵害差止めを求める仮処分事件は含まれないから、仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることはできない旨判示して、本件申立てを却下すべきものとした。
[前提] 特105条の4(秘密保持命令)
特105条の4では、特許訴訟における証拠の偏在に対処するため文書提出命令により立証の容易化を図る一方で、営業秘密について刑事罰を伴う秘密保持義務を課す(特202条の2)ことで、営業秘密の保護を図っています。
具体的には、
①準備書面又は証拠に営業秘密が含まれており、
②営業秘密が開示されることで事業活動に支障を生ずるおそれがあり、
③これを防止するために営業秘密の使用又は開示を制限する必要があり、
④当事者が当該営業秘密を取得又は保有していない場合に、
秘密保持命令の申立により、決定で秘密保持命令を出すことができます。
本事件の要旨
最高裁は、原審の判断を以下の理由により否定しました。
特許法が、刑罰による制裁を伴う秘密保持命令により、営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用すること及び同命令を受けた者以外の者に開示することを禁ずることができるとしている趣旨は、営業秘密を保有する当事者が、相手方当事者により営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は第三者に開示されることによって、事業活動に支障を生ずるおそれがあることを危ぐして、当該営業秘密を訴訟に顕出することを差し控え、十分な主張立証を尽くすことができない事態を回避するためである。
特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件について、上記のような事態が生じ得ることは本案訴訟の場合と異なるところはなく、秘密保持命令の制度がこれを容認していると解することはできない。
そして、仮処分事件において秘密保持命令の申立てができると解しても、迅速な処理が求められるなどの仮処分事件の性質に反するということもできない。
特許法においては、「訴訟」という文言が、本案訴訟のみならず、民事保全事件を含むものとして用いられる場合もある(特54条2項、特168条2項)。
特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は、特105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し、仮処分事件においても秘密保持命令の申立てが許される。
私見
仮処分申し立て事件における秘密保持命令自体が出題される可能性は低いと思われますが、ゼロではありません。また、短答試験で出題される可能性は十分にありますので、少なくとも結論は覚えておきましょう。
つまり、仮処分事件においても、訴訟の追行以外の目的での営業秘密の使用又は第三者への営業秘密の開示によって、事業活動に支障を生ずるおそれがあることを危ぐして、営業秘密の保有者が、当該営業秘密を訴訟に提出することを差し控え、十分な主張立証を尽くすことができない事態が生じ得る。
よって、特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てが許される、ということです。
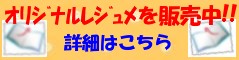
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
リンク
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る